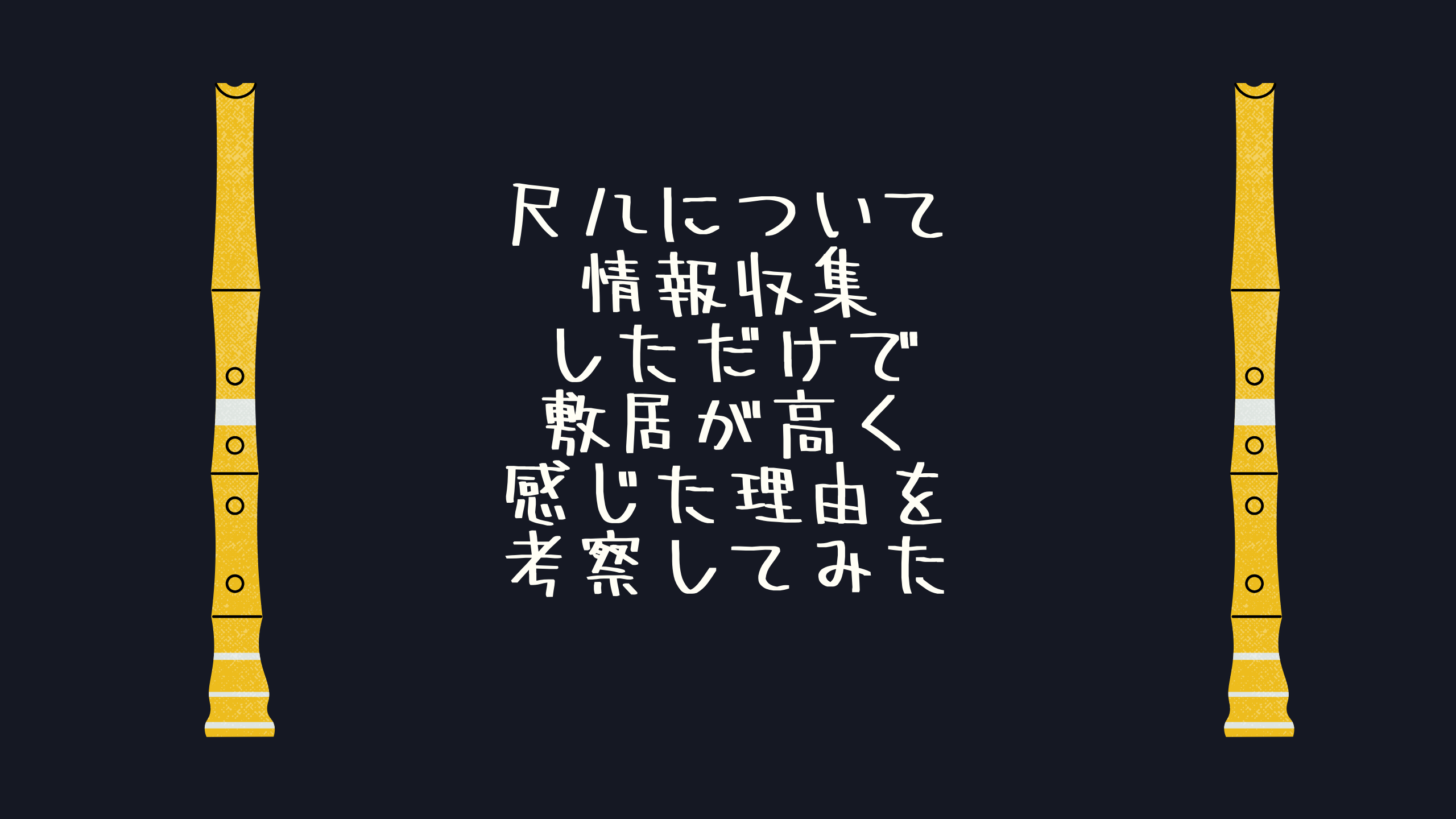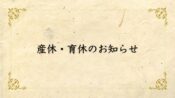尺八について情報収集しただけで敷居が高く感じた理由を考察してみた
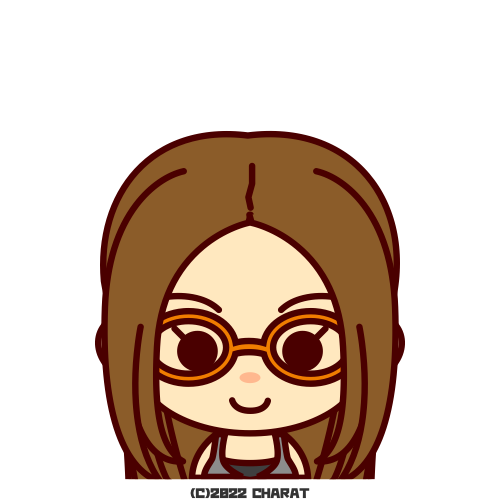
尺八って実はYouTubeでも外国人の先生が存在するレベルでじわじわと世界的に盛り上がっていること、知っていましたか?
私も、HannesのYouTubeお気に入りを見て初めて知りました(笑)
今では尺八って学校の義務教育にも導入されているようです。
しかし、私のような30代、ましてや20代とかの人になると、イマの義務教育は受けなおせません。
本当に残念ですが、興味を持っても学校で学びなおせません。
尺八については夫Hannesの専門領域なのですが、パートナーとしてHannesが熱心に学んでいる尺八について私もちゃんと知りたい!
それに、尺八ってそもそもどんな歴史があるんだろう!?
などなど、深堀りしたくなったんですよね。
そう思ってまずは本を読んでみたかったのですが、なんとまぁ情報を集めることですら敷居が高かった!!
今回はそんな体験談をブログにしたいと思います。
Chichanが尺八について真剣に知見を得ようと思ったきっかけ

私の場合、尺八に触れたりコンサートに行ったのは、夫Hannesとの交際時からです。
それまでは、
- 虚無僧が吹いているヤツ
- 竹切った楽器
- おじいちゃんの趣味(ごめん
って思ってました。(ほんとごめん)
でも、Hannesが辛くも楽しそうに師匠とのレッスンをやっている姿を見て、私も「ふーん」ではいられなくなっちゃったんです。
何より、

と言って、外国人人尺八講師のYouTubeチャンネルをお気に入りしているレベルなので、私自身も知っときたいなーちゃんとって思ったんです。
日本語でも情報が少ないのに、英語の教材もほぼゼロ(YouTubeくらい)
尺八の教材に対しての質問に答えられなかった(笑)
なので、私自身もHannesに意味を問われることがありますが、まーこたえられませんでした😂
先日、尺八の孔って何と読むかについて聞かれたんですが、孔(こう)と呼んでいました(しかも自信なさげに)
尺八の孔って書いて、”あな”と読むんですね……!
Chichan、尺八について知識を蓄えようとしてちょっぴり挫折なう😂

はい、私尺八について知ろうと思って本を読み始めたんですが、もう挫折しそう😂
なぜかというと、ネット上に情報がめっちゃ少ない。
茶道とか着物とか盆栽、書道、禅、華道、三味線、歌舞伎…
この辺りはネット上でも結構な情報量があるのに、尺八、どうした!?レベルで少ないんですよ。
義務教育で尺八を教える前に、これから入り口をチラ見しようとする大人向けにももっと情報ちょうだいよ!って思ちゃったんです。
都山流の教則本を読んでみることからスタートしようと思ったんだが……?
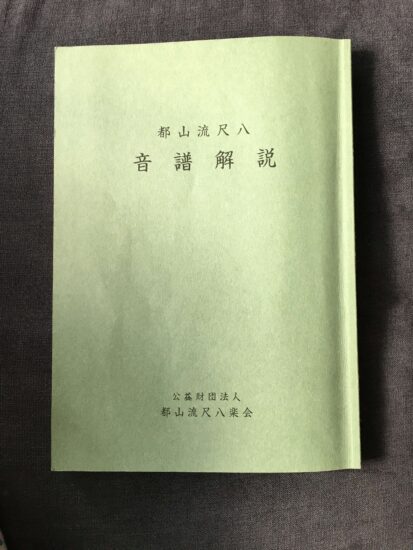
Hannesの教則本
Hannesはひょんなことから、都山流のヤングな先生からオンラインで尺八を学んでいます。
なので、彼は都山流の音譜解説本も日本から持ち帰っているので、いつでも読めます。
せっかく教材もあるし……と思って開いてみたのですが、
- 尺八を既に先生から習い始めている人向け
- 文章がとにかく教科書みたい
ってことで、わずか数分でそっ閉じでした。
そりゃ、教則本だからしょうがない!
しょうがないけど、未経験者や初心者が興味を持てるような内容ではなかったというのが私の意見😢
ちなみに、外国人であるHannesは、教則本の内容を全て英訳してもらったり、先生から学んでいるわけではないようです。
マジで尺八の曲をひたすらに練習して体で技術を身につけています。
ある意味すごいなぁと思ったChichanだったのでした。
尺八が若い世代にとって敷居が高く感じられる理由について主観的に考察してみた

私の経験から考察したところ、こんな感じにまとめられるなーって思っています。
- お金持ちの趣味って思われている
- わかりやすい初心者向け書籍ほぼゼロ
- 口伝えな部分がまだ残っている
- 先生があまりネット進出していない
逆に、上記さえ何らかの形で払しょくできれば、もっと若い世代にも敷居が低くなって、浸透するんじゃないかって思っています。
ちょっと深堀りしてみましょう。
お金持ちの趣味に思われてる
これが最大の要因なのかもしれません。
先日、Hannesの尺八の値段を聞いてひっくり返りそうになりました。

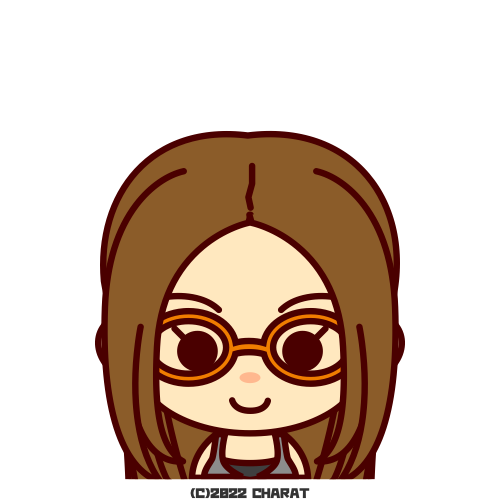
尺八って安いものもあれば高いものもありますが、ホンモノの竹を使ったもので数十万から数百万する代物!
それに、おじいちゃんの趣味ってイメージがあるのはきっと、社会人としてある程度稼ぎのある人がポーンと尺八を購入して、コミュニティセンターでやっているっていう方程式が成り立っているから??かも???
最近ではプラスチック製や木製の尺八も出ているようですが、素人が手を出しにくいのはココに最大の要因がありそう……
(あくまで私の主観ではあるものの……)
わかりやすい初心者向け書籍がほぼゼロ
前述の都山流の音譜解説本が素人のChichanにとってほぼ理解不能かつ興味をそそられなかったように、素人向けかつ、面白いと思わせてくれるわかりやすい一般書籍がほぼ皆無。
Amazonで検索してもほぼ出てこない!!!
これには衝撃を受けました。
今のところ1冊だけ!!!
1冊だけすごく初心者でもわかりやすいように書いてある本があったので、今はその本を読んでいます。
尺八を後世に残したいと奮闘している尺八の製管師の方が書いているので、それはもうわかりやすい!
なんだけど、それでも技術的な事とか良質な尺八の選び方っていう項目を読んでいると、初心者は置いてけぼりになっちゃいますね……。
この本については、今度改めてレビューを書いてみたいなって思います^^
口伝え的な部分が色濃く残ってる
Hannes自身が尺八の練習を先生の口伝え状態で学んでいるように、尺八の世界には口伝えで学ぶという部分がまだ残っているみたい。
茶道とか着物などのように、ネット上でもメソッドがしっかり残っている分野だったらよかったんですが、なかなか難しいこともあるようです。
それでも教則本があるので、まだいい方なのかもしれませんが……
もうちょっと素人にも優しい本が欲しいなぁって思ったChichanでした。
尺八の先生があまりネットに進出していない
ネット上で尺八の先生があまりいらっしゃらない印象も受けています。
ChihannesはInstagramアカウントを運用し始めていますが、尺八の先生でアカウントを所持されている方激少ない!!
自身の練習などもあってSNSやホームページ運用が大変かもしれませんが、WEB関係を仕事にしているChichanから見るとこの分野、マジでネットで頑張れは需要あると思うんだけどなぁ。
現に、外国人の尺八の先生や演奏者は自身のYouTubeアカウントを所持していて、頻繁に楽曲や解説動画をUPしています。
なかにはYouTubeコミュニティを活用して生徒を募っている先生もいらっしゃいました!!
あるYouTubeチャンネルでは、尺八の製管師に関する日本のテレビ番組ドキュメンタリーを英語翻訳して発信しています。
(著作権的に大丈夫か心配ではあるが)
世界は広いなぁ~なんて思いつつ、テクノロジーを活用すれば、本当に世界各地から生徒を募れそうだなって思っちゃいました。
まとめ
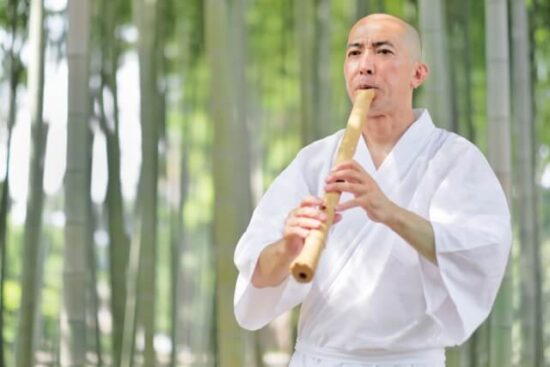
茶道とか盆栽・琴・着物などなど、なんかのきっかけで和文化にふれると、絶対的に尺八の存在が現れるんじゃないかって思います。
歴女なら歴史漫画でも見かけるあのーほら、虚無僧、持ってるじゃない、尺八。
何となく知っているし、見かけるのに、尺八について知ろうとするだけでも敷居が高く感じる理由は、尺八がお金持ちの趣味に見えるというイメージだけでなく、
- 初心者が読んで楽しいと思える一般書籍がほぼゼロ
- 口伝えによって情報が限られている
- 尺八の先生がネット露出あまりしていない
という感じで、広く一般の目に触れる機会が少ないからかもしれない、って考察しています。
逆にそれさえ払しょくしてしまえば、尺八、流行りそうだって思います。
『Chihannes』としても、尺八の魅力を発信出来たらと思っていますので、勉強したことやHannesの練習レポートやインタビューなども随時ブログとして更新できたらって考えています!
ってことで、主観交じりの考察記ブログは以上です!
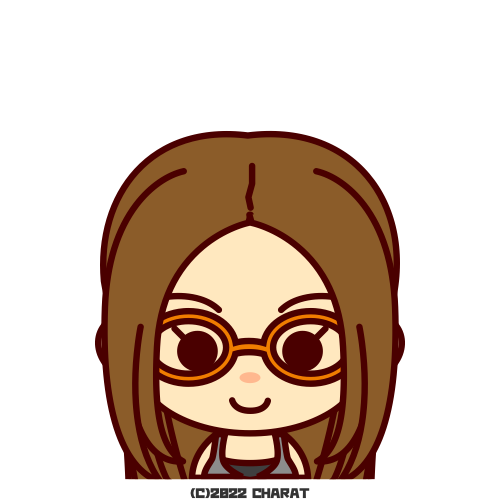
Chichan